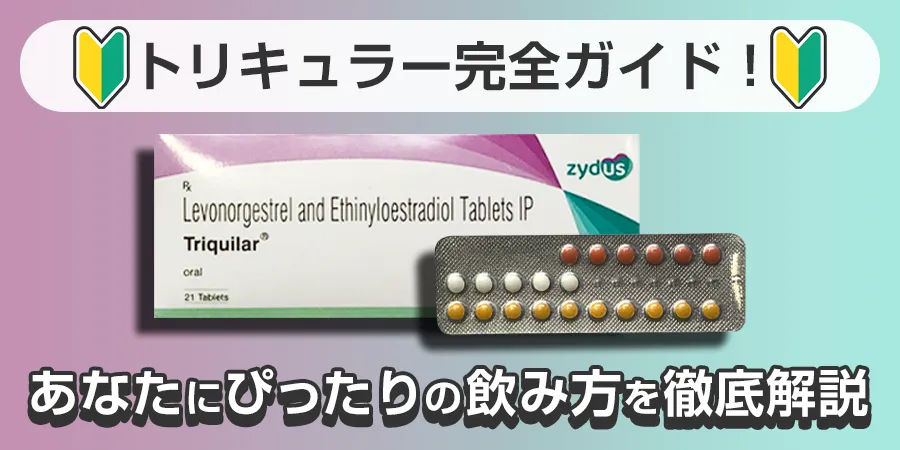低用量ピルの休薬期間とは?休薬期間が必要な理由や無視した場合のリスクを解説
 低用量ピルを利用している多くの人は休薬期間の必要性やその間に起こり得る症状について不安を感じているのではないでしょうか。
低用量ピルを利用している多くの人は休薬期間の必要性やその間に起こり得る症状について不安を感じているのではないでしょうか。
休薬期間に生理がない場合の対処法や、休薬期間を無視した継続摂取のリスクは女性にとって大きな関心事です。
そこでこの記事では、休薬期間の目的と重要性、休薬期間中の体の変化、そして休薬期間を無視した場合の潜在的な影響について詳しく解説します。
低用量ピルの適切な使用方法を理解し、不安を解消したい人はぜひ参考にしてください。
目次 [表示]
低用量ピルの休薬期間とは?
休薬期間とは、一時的に低用量ピルを服用しない期間のことです。
低用量ピルは、1シートに21錠または28錠の錠剤が入っているのが一般的です。
21錠タイプでは最終の錠剤を服用したあと、7日間の休薬期間が設定されています。
一方で28錠タイプは、21錠の有効成分入り錠剤に加え、7錠のプラセボ錠剤が含まれ、このプラセボ錠剤の服用期間が休薬期間に相当します。
いずれの場合も、この休薬期間中に消退出血がおこります。
この休薬期間を設けることで、体内のホルモンバランスが一時的に変動して子宮内膜が剥がれ落ちるためです。
そのため、低用量ピルは服用期間と休薬期間のサイクルを守ることが、正しく服用するうえでなによりも重要になります。
休薬期間が必要な理由
休薬期間には、身体の健康を守る重要な理由があります。
具体的には妊娠の有無を確認し、子宮や卵巣の正常な機能を維持することが理由です。
ここではこの2つの理由について詳しく解説します。
妊娠していないか確認するため
低用量ピルの主要な効果は、排卵を阻止して避妊することにありますが、それ以外にも重要な役割があります。
ピルを継続して使用した場合、その影響で子宮内膜が薄くなります。
そして休薬期間として一時的にピルの服用を止めることによって、子宮内膜が剥がれ落ち消退出血が起こるのです。
この消退出血が起きるということは妊娠していないという証明となるため、消退出血の有無を確認することは休薬期間を設ける大きな理由の一つとなります。
子宮や卵巣の働きを保つため
低用量ピルの服用を継続した場合、一時的に卵胞の成熟と排卵が抑制され月経周期が停止した状態になります。
つまり、卵巣や子宮の機能が休止状態に近くなるのです。
そこで、休薬期間中に低用量ピルの影響から解放されることで、一時的に卵巣や子宮の機能が正常に戻り、次の周期に備えられます。
適切な休薬期間があることで、卵巣と子宮は定期的に休息を取り、正常な働きを維持しています。
低用量ピルの休薬期間のどのタイミングで生理がくる?
 通常、最後にピルを服用してから数日後に消退出血(生理)が始まります。
通常、最後にピルを服用してから数日後に消退出血(生理)が始まります。
具体的には、休薬期間に入ってから3日目ごろから出血が始まるケースが多いです。
個人差はありますが、4日目には大半の人で生理が来ていると考えられます。
出血量や期間には幅があり、3日間程度で収まる人もいれば、7日近く続く人もいるでしょう。
生理の時期はピルや個人の体質によっても変わってくるため、あくまでも目安となります。
休薬期間明けにピルの服用を再開することで、再び徐々に生理は止まっていきます。
出血が長引く場合は、何らかの異常の可能性もあるため医師に相談することが賢明でしょう。
生理の有無や時期を把握し、適切に対処することが大切です。
休薬期間中に生理がこないときはどうすればいい?
休薬期間に生理がこないときは、いくつかの原因が考えられます。
ここでは、その原因と、生理が来ないときの具体的な対策について確認しましょう。
休薬期間中に生理がこない原因
休薬期間に消退出血がおきない場合、最初に考えられるのは妊娠の可能性です。
低用量ピルは適切に服用すれば99%以上という非常に高い避妊率を誇るものの、極々稀に妊娠してしまうケースがあります。
次に、服用期間が長くなるにつれて、出血量が徐々に減少していく傾向にあることが原因の場合もあります。
ホルモンバランスの乱れにより、子宮内膜が十分に剥がれなくなって出血が起こりにくくなるという仕組みです。
また、過度のストレスや体調不良、急な体重変動、不規則な生活リズムなども生理不順の一因となり得ます。
さらに、ピルの服用が不規則だった場合や、飲み忘れが続いていた場合も、生理不順となる原因の1つです。
ホルモン剤の影響が安定しないため、子宮内膜の状態に変化が起きて消退出血が起きない可能性があります。
休薬期間中に生理がこないときの対策
休薬期間から予定の日数が経過しても生理がこない場合、まず妊娠の可能性を考えて妊娠検査薬で確認しましょう。
検査の結果、妊娠している場合は産婦人科を受診し適切な対応が必要です。
反対に、検査で陰性だった場合は次の対策を試みましょう。
前回の生理からの経過日数をチェックし、生理不順の程度を確認することが大切です。
場合によっては、ホルモン検査や超音波検査を受けるために受診する必要があるかもしれません。
妊娠の可能性がなく、ほかに特別な問題が見られなければ、服用を続けても差し支えないでしょう。
ただし、次の期間で生理が来るかどうかは注意深く観察する必要があります。
低用量ピルの休薬期間中も避妊効果は継続する?
低用量ピルの主な作用は卵胞の成熟と排卵の阻害による避妊であり、休薬期間もこの避妊の効果は一定程度保たれるとされています。
ただし、完全に避妊効果が維持されるわけではありません。
休薬期間になると体内のホルモンの状態が変化し、次第にピルの影響が薄れていきます。
そのため、休薬期間中に性交渉を行うという場合には、避妊効果を過信せずに他の避妊方法を併用するなどの対策を行うことが賢明といえます。
低用量ピルの休薬期間を無視して飲み続けられる?
休薬期間を無視して連続で飲み続けた場合、いくつかの問題が生じる可能性があります。
ここでは、休薬期間を無視した場合に生じる不正出血の可能性や休薬期間が短いピルの存在について紹介していきます。
不正出血を起こす可能性がある
休薬期間を無視して連続で低用量ピルの服用を続けると、子宮内膜が十分に剥がれる機会がなくなります。
これにより、不正出血のリスクが高くなることは大きな問題といえます。
子宮内膜が剝がれずに次第に厚くなった場合、出血のタイミングが不規則になったり、持続的な出血が起こったりする可能性があります。
このように、月経周期が大きく乱れて生理不順が引き起こされるリスクを把握しておくことが重要です。
また、ピルを絶え間なく服用し続けることで、体内のホルモンバランスが大きく乱れて不正出血の原因となることも考えられます。
さらに、子宮内膜がずっと剥がれずにいると悪性化して子宮体がんになるリスクも指摘されているため注意が必要です。
不正出血は生理不順や貧血、月経困難症などの症状を引き起こす可能性もあり、健康上の問題につながるリスクがあります。
休薬期間が短いピルがある
休薬期間が7日間あるのは長すぎると感じる人も少なくありません。
そこで近年、より短い休薬期間で設計されたピルが登場しています。
より自然な生理周期に近づけ、不正出血のリスクを抑えられるようデザインされているのが特徴です。
ヤーズフレックスは休薬期間が4日間となっており、短い期間で次のシートに移行可能です。
しかし、休薬期間が短すぎると、子宮内膜が十分に剥がれず、不正出血のリスクが高くなる可能性もあります。
休薬期間の長さには個人差があり、各自の体質に合ったタイプを選ぶことが大切です。
まとめ
低用量ピルには一定期間の休薬期間が設けられており、妊娠の有無を確認したり子宮と卵巣の機能を保ったりする役割があります。
休薬期間に入ってから2〜4日後に消退出血がおこり、次の服用開始とともに止まるのが一般的です。
生理が来ない場合は、妊娠の可能性や体調不良などが考えられるため対応が必要です。
また、休薬期間を無視して連続服用を続けると不正出血のリスクが高まるでしょう。

低用量ピルは休薬期間がきちっと定められています。休薬期間をきっちり守って正しく服用しましょう!低用量ピルは基本的には不要になるまで使うもの。だからこそコストを抑えたいという方は通販で低用量ピルを購入するのがオススメ!
監修者情報

監修者
河井 恵美
所属・資格等
助産師・看護師・保育士・公認心理師
経歴
この仕事が大好きで、25年以上看護師・助産師として働いてきました。
日本では大学病院、市民病院、個人病院等で様々な診療科を経験し、看護教育や思春期教育、行政の仕事にもかかわってきました。
海外では、アフリカやアジア圏で医療活動をした経験があります。
現在は、海外に住む日本人の妊婦さんや親御さん向けにオンラインクラスなどを行うエミリオット助産院を運営しています。
親御さんへのアドバイスを充実させるために保育士や公認心理師の資格を取得して役立てています。
正しく役に立つ情報を提供したいという思いから、積極的に妊娠・出産・育児に関する記事の執筆・監修などを行っています。