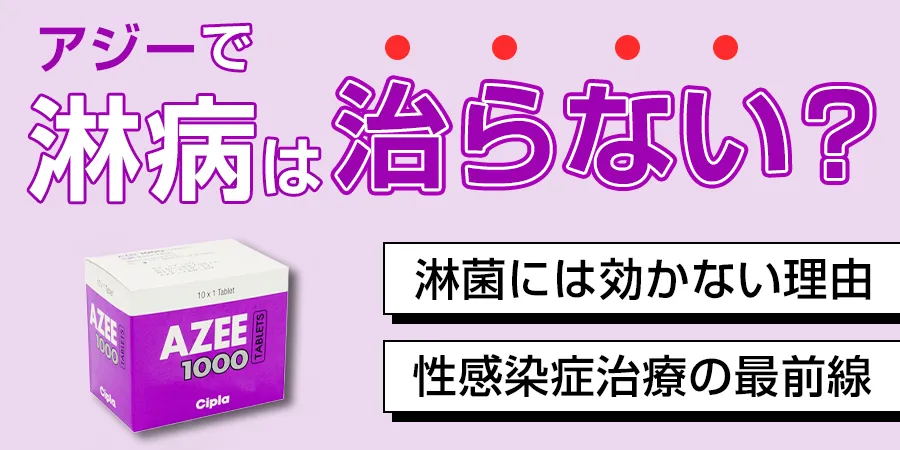カンジダの症状を感染部位別に徹底解説!カンジダを予防する方法とは?
 カンジダ症は、女性に多い性感染症のひとつですが男性・女性問わず感染します。
カンジダ症は、女性に多い性感染症のひとつですが男性・女性問わず感染します。
性器やのど、食道などのさまざまな部位に感染するため、感染部位ごとの適切な予防方法について知ってくことが大切です。
この記事では、感染部位ごとのカンジダ症の症状や予防策について解説します。
カンジダ症を発症しないために予防したい人は参考にしてください。
目次 [表示]
そもそもカンジダとは?
カンジダとは、人の体のさまざまな部位で見られる真菌の一種です。
まずはカンジダの基本的な概要と、その発生原因について解説します。
参考元:カンジダ症
カンジダの概要
カンジダとは、人体に常在する真菌の一種です。
通常は無害な存在ですが、体の抵抗力が低下した場合、カンジダ菌が過剰に増殖して感染症を引き起こします。
感染しやすい部位としては腟や口腔内、消化管などの粘膜部位が挙げられます。
高温多湿の環境下で合成繊維の下着を着用していたり、不衛生な状態が続いたりといった条件下ではカンジダが繁殖しやすくなります。
また、抗生物質や免疫抑制剤の長期的な使用、糖尿病をはじめとする免疫力を低下させる病気を患っている場合も、カンジダ症を発症するリスクが高まります。
重症化した場合、カンジダ菌が血液のなかに入り込む「カンジダ血症」と呼ばれる深刻な状態に陥る可能性があり、場合によっては生命の危険すらある危険な病気です。
カンジダの原因
カンジダ症の原因は、発症した部位によって異なります。
口腔や食道のカンジダ症は副腎皮質ステロイド薬の投与や糖尿病などで免疫力が低下した際に、常在菌のバランスが崩れてカンジダが増殖することが主な原因です。
喘息治療薬のコルチコステロイド吸入薬の使用でも発症しやすく、HIV感染症の合併症としてもよく見られます。
性器のカンジダ症は抗菌薬や糖尿病の合併症、ステロイド剤の投与がきっかけとなることもあります。
妊娠中や免疫力が低下している状態、生理前や性行為の刺激、ナプキンの長期使用などもカンジダ症が発症する要因となります。
感染部位別のカンジダの症状
カンジダの感染は体のさまざまな部位に影響を及ぼすことがあります。
ここでは感染部位別にカンジダ感染が引き起こす具体的な症状を詳しく見ていきましょう。
【女性】性器
腟はもともとカンジダ菌が存在する場所ですが、免疫力の低下や抗菌薬の使用などでカンジダが過剰に増殖した場合、外陰部から腟にかけての不快な症状があらわれます。
主な症状としては外陰部や腟のかゆみ、白色のヨーグルト状のおりものの増加、陰部の炎症による痛みや性交渉時の痛みなどです。
ほかにも、排尿時に違和感がある場合もあります。
風邪や疲労、ストレスによる免疫低下や妊娠中の体内環境の変化などがカンジダ症の発症につながる要因です。
一度発症した場合、再発を繰り返すケースも見られるでしょう。
参考元:性器カンジダ症の治療方法
【男性】性器
男性においても、カンジダによる性器感染症が発症することがあります。
不衛生な状態が続くと、亀頭にカンジダ菌が付着して炎症を起こします。
主な症状は、亀頭のかゆみやただれ、赤み、カサブタの発生、白色の分泌物の増加などです。
包茎の場合、雑菌や湿気がたまりやすいためカンジダに感染するリスクが高くなります。
稀に尿道炎を発症し、排尿時や性行為時に違和感、痛みを感じることもあるでしょう。
包茎や糖尿病、ステロイド剤の長期使用などが、男性器のカンジダ症を引き起こす原因となっています。
【男女共通】のど
カンジダ菌が口腔内や咽頭部に増殖した場合、のどにさまざまな症状があらわれます。
初期段階では、のどの渇きや鈍い痛みなどの軽微な違和感にとどまりますが、炎症が広範囲に及ぶと、出血や激しい痛みを伴い、飲み込むことさえ困難になる可能性があります。
のど粘膜に赤みを帯びた白い斑点が多数見られ、こすってもなかなか落ちないのが特徴です。
病状がさらに進行した場合、口蓋や頬、舌にも同様の症状が広がっていきます。
また、食道方向へ感染が拡大すれば、飲み込む動作がいっそう辛くなります。
【男女共通】皮膚
皮膚にカンジダ菌が感染した場合、かゆみや発赤、腫れなどのさまざまな症状が見られます。
発症しやすい部位は、湿気が多く通気性の悪い陰部や指の間、おむつ周りの股部など常に湿った環境におかれている皮膚です。
免疫力の低下や高温多湿の環境、不潔な状態が続くことでカンジダ菌が増殖して感染症を引き起こします。
特に赤ちゃんはおむつの着用により発症するリスクが高いです。
皮膚カンジダ症の治療には主に外用の抗真菌薬が使用されますが、症状の重症度や感染範囲によっては内服薬の投与が必要になる場合もあります。
重症化や再発を防ぐには、適切な治療を早期に受けることが重要です。
【男女共通】指先
指先の爪周りの柔らかい皮膚部分にカンジダ菌が感染した場合、赤みや腫れ、痛みなどの症状があらわれます。
爪そのものが白く濁って見える場合もあります。
このような爪カンジダ症は、半年から1年ほどで自然に治癒することが多いとされていますが、爪白癬(水虫)と間違えられがちなため検査を受けて菌種を特定することが大切です。
治療法としては、主に外用の抗真菌薬や薬用爪用剤を使用します。
長期に渡る場合は内服薬の投与も検討されるでしょう。
【男女共通】食道
口腔内からカンジダ菌が食道に感染し、そこで増殖すると食道カンジダ症と呼ばれる状態になります。
主な症状は、食べ物を飲み込む際の違和感や胸やけ、胸の奥が痛むなどです。
症状が進行すれば、飲み込む動作そのものにも激しい痛みを伴うようになります。
食道カンジダ症には自覚症状がないことも多く、内視鏡検査で偶然発見されるケースもあります。
食道粘膜が白苔で覆われているのが特徴です。
免疫力が回復すれば自然治癒する可能性もありますが、基本的には抗真菌薬の内服や点滴投与による治療が必要となります。
感染部位別のカンジダの予防方法
先述した通りカンジダは、性器やのど、食道など体のさまざまな部位に感染する可能性があります。
ここからは、感染部位ごとのカンジダの予防方法について解説します。
性器
性器のカンジダ症を予防するには、まず陰部を清潔で乾燥した状態に保つことが大切です。
通気性のよい素材の下着を着用することで、蒸れによる発症リスクを下げられるでしょう。
特に夏場は注意が必要です。また、性行為を行う際にはコンドームの着用により、感染の拡大も防げます。
ただし、過剰な陰部の洗浄は避けましょう。
腟内にも有益な常在菌が存在しており、洗いすぎによってそれらを流してしまうと、かえって悪影響を及ぼす可能性があるためです。
参考元:膣カンジダってどんな症状?
のど
のどのカンジダ症を予防するには、口腔内を清潔に保つことが重要です。
定期的な歯磨きや、口腔ケアによりカンジダ菌の増殖を抑制できます。
特に義歯を使用している場合は、バイオフィルム形成による感染リスクが高まるため義歯の手入れには細心の注意が必要です。
単なるブラッシングでは不十分なため、専用の洗浄剤や超音波洗浄器を用いるとよいでしょう。
また、喘息治療でステロイド吸入薬を使う際は、うがいと並行して口腔粘膜のこすり洗いも心がけましょう。
口内が乾燥しがちな場合は、水分補給やうがい液の使用で乾燥を防ぐよう意識することも大切です。
皮膚・指先
皮膚や指先のカンジダ症の予防についても、日頃から清潔で乾燥した環境を保つことが大切です。
皮膚の清潔さを保ち、汗をかいた際にはこまめに拭き取るといった湿った状態が続かないよう気をつける必要があります。
特に指の間はカンジダ菌が繁殖しやすい状況となるため手入れには十分注意を払いましょう。
参考元:皮膚カンジダ症について
食道
食道のカンジダ症を予防するには、まず体内の免疫力を維持することが大切です。
適度な運動と規則正しい生活リズム、バランスの取れた食事を心がけましょう。
また、食道粘膜を刺激する濃い味付けの辛い食べ物や刺激物、甘味の強い食べ物なども控えめにすることも大切です。
食道カンジダ症は抗真菌薬の投与で比較的短期間で症状が改善されるとされていますが、早期発見と適切な治療、予防対策を怠らず健康的な生活習慣を心がける必要があります。
まとめ

カンジダ症は、カンジダ菌という真菌が過剰に増殖することで起こる感染症です。
免疫力の低下などが原因で性器やのど、皮膚、食道といった体のさまざまな部位に発症する可能性があります。
代表的な症状は発赤や分泌物の増加、かゆみなどです。
食道やのどにカンジダ症が発症した場合は、痛みにより飲み込みが困難となる場合もあるでしょう。
適切な治療を行わないと全身に感染が広がる危険性があるため、早いうちに医師に相談することが大切です。
性器や皮膚は乾燥を心がけ、口内は歯磨き・うがいで清潔を保ち、免疫力を高める食事や運動など日頃からの清潔な生活習慣が予防するうえで重要です。

カンジダ菌は性器だけでなく、のどや食道にも感染します。だからこそカンジダに感染していると分かった段階での治療が大事!カンジダの治療薬は通販サイトで購入することができます!