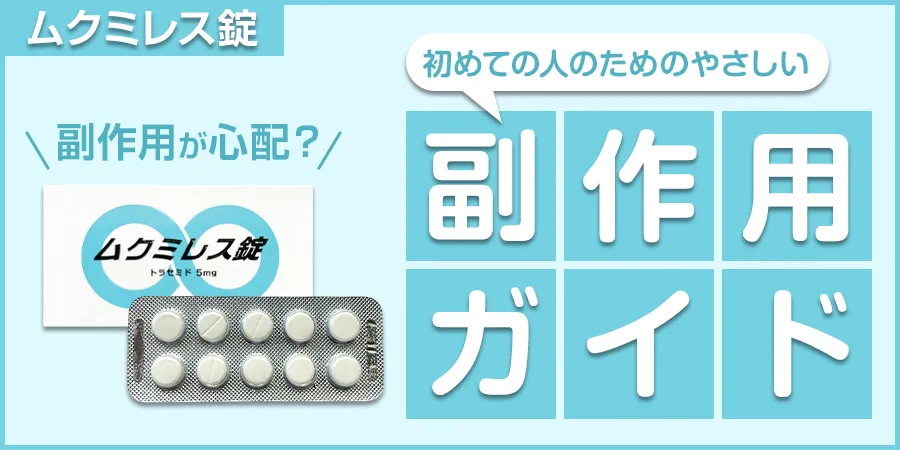むくみの原因とは?原因10選と部位別の原因&対処法を解説!
 今回のテーマは「むくみ」です。
今回のテーマは「むくみ」です。
「朝起きたら、顔も足もパンパン……」
そんな経験をお持ちの方、また実際に悩まれている方は多いと思います。
むくみには、さまざまな原因があります。
その原因を知り、対処することができれば、日常的に起こるむくみから解放されるかもしれません。
この記事では、むくみの原因と対処についてご紹介します。
顔や足、手や指など部位別の対処方法についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次 [表示]
一過性のむくみの10の原因

ここでは、日常的によく見られる一過性のむくみの原因について解説します。
実は多くの場合、生活習慣や食習慣が原因になっているパターンがほとんどです。
普段から無意識に行ってしまっていることがないか、チェックしてみましょう。
長時間同じ姿勢をとっている
長時間同じ姿勢をとっていると、血液の循環が悪くなり、体内の水分が下半身に溜まっていきます。
「長時間同じ姿勢」と聞くとデスクワークを連想される方が多いと思いますが、立ち仕事でも同様の事象が起こります。
特に、ヒールを履いて仕事をしている方は要注意です。
ヒールを履いていると、体の重力が余計に加わってしまい、ふくらはぎがむくみやすくなります。
水分のとりすぎ
人が健康的に生きるためには水分の摂取が欠かせませんが、とりすぎるとむくみを起こすことがあります。
摂取した水分のうち、不要なものは尿などで排泄されますが、摂取しすぎると排泄が追いつかず、体にたまってしまいます。それがむくみとなる仕組みです。
ちなみに、1日に必要な水の量は体重1kgに対して35ml程度とされています。
体重60kgの人なら、約2.1リットルです。
これを目安に、大幅に超えないように心がけましょう。
塩分のとりすぎ
人間の体には体内の塩分濃度を調整する働きがあり、塩分が多いときは水分で濃度を下げようとします。
こうして水分を体にため込もうとすることで、むくみが起こります。
ちなみに、塩分の過剰摂取で起こるむくみは目の周りに出ることが多いため、「まぶたが重い……」と感じることが多い人は、塩分を控えるようにしましょう。
運動不足による筋力低下
運動不足が原因で筋力が低下した状態になると、血液の循環が悪くなってむくみが発生します。
特に、下半身の筋力低下はむくみを起こしやすいため、注意が必要です。
一時的な場合はこのあと紹介するストレッチ、エクササイズなどで改善されますが、加齢が進むとなかなか筋力が戻りにくくなるため、日ごろから意識して足を動かすようにしましょう。
睡眠不足
あまり気にされていない方も多いのですが、睡眠とむくみには深いつながりがあります。
睡眠が不足すると自律神経が乱れ、心臓などの内臓機能が低下します。
その結果、血流が悪くなってむくみが起こるのです。
睡眠不足が原因のむくみの場合、足、また顔がむくみます。
年齢、体質など個人差はありますが、私たち人間の適切な睡眠時間は1日あたり6~8時間といわれています。できるだけ十分な睡眠をとれるように心がけましょう。
アルコール・睡眠前の飲酒
お酒を飲むと血管内の水分が不必要に排出されてしまい、アルコールの血液濃度が高くなります。
すると、体は濃度を下げるために再び血管内に水分を大量に取り込みます。
これが、アルコールによってむくみを生じるメカニズムです。
また、アルコールには利尿作用があるため、盛んにトイレに立つことで水分がどんどん失われてしまいます。
その結果、体がこれ以上は水分を失うまいと、今あるだけの水分をため込もうとします。
これがむくみの発生につながります。
無理なダイエット
ここでいう無理なダイエットとは、極端な食事制限などを指します。
食事制限によって必要な栄養素が摂取されなくなることで、むくみが引き起こされます。
具体的な理由として挙げられるのは、水分調整に必要な栄養素が十分に摂取できなくなること。
体内の適切な水分量を維持できなくなった結果、不要な水分がたまってむくみになってしまうという仕組みです。
きつめの服や靴
タイトすぎる服を長時間に渡って身につけていると、体の血管が狭まって血行が悪くなります。
そして血行が悪くなった結果、むくみを起こすことがあります。
特に足のむくみは、靴がきつすぎることが原因であるパターンが少なくありません。
自分の体に合ったサイズのものを身に着け、不必要に体をしめつけないようにしましょう。
参考元:むくみが気になる人へ
身体の冷え
身体が冷えると、足先の毛細血管まで十分に血液が行き届かなくなります。
その結果、血液やリンパの流れが悪くなり、むくみが起こります。
「冷え」と聞くと冬場の寒さを思いうかべる方が多いと思いますが、夏場のクーラーが効いた部屋も注意が必要です。
- 部屋を冷やしすぎないようにする
- 靴下を履く
このようなことを心がけ、足を冷やさないよう注意しましょう。
ストレス
ストレスを感じると、「ストレスホルモン」と呼ばれるコルチゾールが分泌されます。
コルチゾールは、糖や脂質の代謝に関わる重要なホルモンですが、分泌量が増加するとさまざまな不具合を引き起こします。
そのひとつが、血管やリンパ管の外壁部分を構成する細胞の接着を緩めることです。
外壁に隙間ができて水分が血管やリンパ管の外に漏れ、たまってしまうことでむくみが生じるわけです。
慢性的なむくみの原因

一時的なむくみではない場合、体の中では重い病気が進行している可能性があります。
ここでは、慢性的に起こるむくみの原因について解説します。
「毎日むくんでいる……」という方はぜひチェックしてみてください。
心臓の疾患や障害
心臓機能が低下すると血行が悪くなり、全身に水分が溜まります。
代表的な疾患として挙げられるのは「心不全」で、ちょっと歩いただけで息切れをしたり、体力の低下が感じられるといった症状がある場合、その前兆が疑われます。
むくみに関しては、全身に溜まった水分は下に移動する性質があるため、特にすねやふくらはぎなどの下半身に現れるのが特徴です。
また、指でむくんでいる場所を押すとへこんで痕が残り、なかなか元に戻らないという特徴があります。
肝臓の疾患や障害
肝臓は、主に以下のような機能を担っています。
- 解毒
- 胆汁を生成する
- アルブミンを生成する
- 栄養素の代謝を促す
むくみと関係しているのは、「アルブミン」です。
アルブミンは血液中に存在するタンパク質の一種で、体内の水分を正常に保つために必要な物質です。
肝臓機能が低下し、「肝硬変」「肝臓がん」などの病気を発症すると十分に生成されず、体内の水分調整がうまくいかなくなり、むくみが表れます。
腎臓の疾患や障害
腎臓の主な役割は、「尿の生成」です。
「急性腎炎」「慢性腎炎」「ネフローゼ症候群」などの病気になっている場合、尿を作り出す機能が低下し、本来なら排出しなければならない水分や毒素が体内に溜まります。
水分が溜まった状態がむくみとしてあらわれるのですが、この場合、全身がむくむだけでなく、体重の増加や倦怠感なども表れます。
リンパ浮腫
体内には血液のほかに「リンパ液」が流れています。
体内で生じる老廃物を運ぶのが役割で、リンパ管を通っていますが、がんの治療などの影響でリンパ管をつなぐ「リンパ節」の働きが低下することがあります。
リンパ管やリンパ節に何らかの障害が起こると、リンパ液の流れが悪くなり、過剰に溜まります。
過剰に溜まったリンパ液が皮下に染み出して起こるのが「リンパ浮腫」です。
胸、背中、手足などにみられるのが特徴です。
下肢静脈瘤
下肢静脈瘤は、足の血管に起こる病気です。足の静脈が太くなって瘤状に浮き出て見える状態が「下肢静脈瘤」で、この病気を発症すると血流が悪くなり、むくみが表れます。
命にかかわるような病気ではないといわれていますが、慢性的に足がむくむことで疲れやすく、倦怠感を伴うこととなります。
深部静脈血栓症
深部静脈血栓症とは、筋肉の間にある「深部静脈」に血の塊(血栓)ができてしまう病気です。
静脈における血液の流れがせき止められることでさまざまな症状を引き起こしますが、そのひとつがむくみです。
深部静脈血栓症が起きてすぐの時期は、強い痛みや皮膚の色の変化などが症状として現れます。
その時期を過ぎると、皮膚の色が紫色になる(静脈血がたまるため)、むくみなどが発生します。
男性より女性の方がむくみやすい、ってホント?

「むくみといえば女性が悩むもの」というイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。
実際のところ、男性よりも女性のほうがむくみやすい傾向にあるのは確かです。
ここでは、その理由について解説します。
筋肉が男性より少ない
むくみの直接的な原因のひとつとして「血行の悪さ」が挙げられますが、女性は男性に比べると血行不良になりやすい性質を持っているとされています。
というのも、一般的に筋肉量が男性に比べて少ないからです。
特に下半身の筋肉は、血液を心臓まで押し上げるポンプの役割を担っていますが、女性は男性に比べると筋肉量が少なく、ポンプの機能が比較的低いといえます。
そのため、ちょっとしたことで血行不良を招きやすく、むくみやすいといえます。
女性特有のむくみの原因
男性にはない女性ならではのむくみの原因としては、「生理」が挙げられます。
上記のように、むくみの主な直接原因のひとつは血行不良であるわけですが、生理開始前や生理中に強いストレスや緊張を感じると血流が悪くなることがあります。その結果、むくみが出るわけです。
また、生理前には黄体ホルモンの分泌量が増えることで体内に水分がたまりやすくなる性質があります。ここでたまった水分がむくみとしてあらわれることがあるのです。
【部位別】むくみの原因と症状
ここまで、いろいろなむくみの原因について解説してきましたが、ここからはむくみが起こる部位ごとの原因、症状について解説していきます。
特に多い顔、足、手(指)の3ヶ所についてまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。
顔のむくみの原因と解消方法
顔がむくむ原因と解消方法について、一過性のものと慢性的なものと2つに分けて解説します。
慢性的なむくみには重い病気が隠れている可能性があるので、早めに病院に行くようにしてください。
顔がむくんでしまう原因(一過性の場合)
顔のパーツのうち、最もむくみやすく、見た目に分かりやすいのは「目もと」です。
原因としては、次のようなことが考えられます。
- アルコールのとりすぎ
- 塩分のとりすぎ
- 睡眠不足
また女性の場合、ホルモンが影響することもあります。
この場合、このあと紹介するマッサージで改善が見込めるので、ぜひ試してみてください。
顔がむくんでしまう原因(慢性的な場合)
1週間以上むくみが続く場合、「慢性的なむくみ」と判断することができます。
考えられる原因は甲状腺や肝臓の病気などです。また、女性の場合は月経前に起こりやすい他、更年期でもホルモンバランスを崩して慢性的にむくんでしまうこともあります。
「一過性の場合」で挙げたような原因がないにもかかわらず慢性的にむくんでいる場合、一度医師に相談してみましょう。
顔のむくみを解消する方法
顔のむくみの解消法としては、ゆっくり湯船に浸かったり、運動をしたりといったことが挙げられますが、いちばんのおすすめは「セルフマッサージ」です。
時間をかけず、手軽に行うことができるため、「時間がない!」という方にもおすすめです。
方法は簡単です。
- 肩と首をゆっくり回し、目の下から後頭部にかけて優しく指で押していきます。
- そのあと、あごから耳、耳から鎖骨の中心にかけて優しくマッサージします。
- 最後は肩の付け根、両鎖骨のあいだから鎖骨の中心にかけて優しくほぐしていきます。
あくまでも、圧をかけ過ぎず優しく行うのがコツです。
足のむくみの原因と解消方法
「仕事柄、足がむくみがち……」
「最近足が太くなっていっている気がする……」
など、足のむくみにお悩みの方は多いかと思います。
ここでは「一過性のもの」「慢性的なもの」と2つに分けて原因と対処法をご紹介します。
足がむくんでしまう原因(一過性の場合)
足、特にふくらはぎは男女ともにむくみやすい部位です。
原因として挙げられるのは、以下の通りです。
- 長時間同じ姿勢になっている
- 飲酒
- 冷え
- 過度なダイエット
- 運動不足
なお、ここでいう「一過性」とはひと晩寝たら治るもの、また数日でおさまるものを指します。
たとえば「仕事終わりは毎日むくんでいる……」という場合であったとしても、ゆっくり入浴してしっかり睡眠をとれば治ってしまうなら、一過性のむくみといえます。
足がむくんでしまう原因(慢性的な場合)
心臓機能が低下している状態や下肢静脈瘤といった病気を抱えている場合、慢性的なむくみがあらわれることがあります。
心臓機能が低下している状態の代表例は「心不全」ですが、心不全の原因とされる「動脈硬化」「狭心症」「心筋梗塞」なども、足のむくみの原因になります。
早期発見のためにも、日ごろから急な体調の変化を放置せず、医師に相談するなどが大切です。
足のむくみを解消する方法
足のむくみを解消するための方法には、足を心臓より高い位置にして寝るとか、塩分やアルコールを控えるといったことがありますが、いちばんのおすすめは「リンパ流し」です。
まずは床に片膝を立てた状態で座ります。
次に、指の腹で膝の裏をやさしく押してみましょう。
強く押す必要はありません。「気持ち良い」と感じる程度の力で30秒ほど押したら終了です。
30秒あればすぐにできますので、お仕事をされている方もぜひやってみてください。
手・指のむくみの原因と解消方法
最後は手・指がむくむ原因とその解消方法について解説します。
「指がむくんで指輪が食い込んで痛い……」
「最近手がパンパンになってきた……」
という方はぜひ参考にしてみてください。
手・指がむくんでしまう原因(一過性の場合)
手のむくみの主な原因としては、次のようなことが挙げられます。
- 飲酒
- 塩分のとりすぎ
- 水分のとりすぎ
- 長時間のデスクワーク
基本的には左右の手が同じようにむくみます。
特に、日常的に飲酒をされる方は、お酒を飲みながら塩分が濃い食べ物を口にしがちです。
どちらも適度な量を心がけるようにしましょう。
手・指がむくんでしまう原因(慢性的な場合)
一過性の原因として挙げた事柄に心当たりがない場合、腎臓や肝臓の病気、心不全、リンパ浮腫のほかに「関節リウマチ」「甲状腺機能低下症」「妊娠高血圧症候群」などが隠れている場合があります。
上記の病気が原因で手がむくんでいる場合、息苦しさや倦怠感を生じることが多いとされています。
こうした症状も見られる場合はすぐに病院を受診してください。
手・指のむくみを解消する方法
手や指を温めることで解消する方法などがありますが、いちばん効果的なのは「グーパーストレッチ」です。
すぐに実践できるうえ、道具は不要で時間もかからないので、ぜひ試してみてください。
腕を肩の位置まで上げて前に伸ばし、手をグー、パー、グー、パーと交互に開いたり閉じたりする……これだけでOKです。
グーのときはしっかりと拳を握り、パーのときは指を反らせるようにするとより効果的です。
参考元:「手指のむくみ」に効くストレッチ
身体全体のむくみを解消する方法
ここでは全身のむくみを解消する方法を3つご紹介します。
手軽にできる方法をピックアップしてまとめているので、「身体のあちこちがむくんで悩んでいる」という方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
ストレッチ・エクササイズ
むくみが起こる原因はさまざまですが、共通しているのは血液やリンパの流れが不調になることです。
そのため、一過性のもの、慢性的なものにかからず、「体を動かして血行・リンパの流れを良くする」ということがむくみ解消のいちばんの近道となります。
病気で体を動かせない場合を除き、ストレッチやエクササイズは毎日コツコツと続けるようにしましょう。
毎日続けることで、現在起こっているむくみが改善されるだけでなく、体質が改善し「むくみにくい体」を目指すことができます。
特に中高齢者は年々体力が落ちていきますので、今のうちに始められることをおすすめします。
カリウムの摂取
私たち人間には体内に溜まった水分を排出する働きが備わっていますが、体内のナトリウムが増えすぎてしまうと余分な水分が体内に溜まり、「むくみ」となります。
そんなむくみは、野菜やサプリなどでとれる「カリウム」で改善されることもあります。
カリウムをとると体内に溜まった余分なナトリウムが尿として排泄され、むくみ解消を手助けます。
きゅうりやほうれん草、長芋などの野菜にはカリウムが豊富に含まれているので、日ごろからむくみ対策をしたい方はこうした食品を積極的にとるようにしてください。
利尿剤を使用する
そもそもむくみとは、さまざまな原因で発生するものですが、突き詰めていえば、体内にたまった余計な水分によって皮膚がふくらんでいるように見えるというものです。
ということは、たまっている余計な水分を排出することができれば、むくみも解消することができます。
利尿剤には、まさしくそのような効果が期待できます。
この薬は、文字通り尿を積極的に生成して体外に排出させる働きを持っていますが、尿を生成する過程で体内にたまった余計な水分を材料として使います。
つまり、むくみの原因となる余計な水分を、尿として体外に排出させることでむくみを解消するわけです。

身体のむくみを解消するためにはストレッチやカリウムの摂取、そして利尿剤の使用が有効です!むくみに効果のある利尿剤は通販サイトで購入することができます!
まとめ
この記事では「むくみ」をテーマに、その原因と対処法についてまとめてみました。
ポイントをまとめると、以下のようになります。
- むくみにはさまざまな原因がある
- 慢性的なむくみには重い病気が隠れている場合がある
- 女性は男性に比べむくみやすい
- むくみ対策には日ごろのストレッチが有効
特に男性の場合、「大した問題ではない」と思われている方も多いのですが、むくみは体のSOSサインです。解消することでより健康的な生活ができるので、ぜひこの機会にご自身の体と向き合ってみてください。
そのときに、再度この記事でご紹介した内容を参考にしていただければ幸いです。